medscapeの記事(1/31)によると、ACP(アメリカ内科医学会)が、新しいガイドラインを発行したとのこと。
medscape:ACP Issues Guidelines for Diagnostic Imaging for Low Back Pain
腰痛に対してルーチンとして行うX線(レントゲン)撮影、CT、MRIといった画像検査は、患者の健康状態を改善させない。それどころか、害になることもある。
・・・というものだ。
これまでも、画像検査によって腰部痛の原因が分かるわけではないという発表は多くあったとも思う。
しかし、やはり医療側として「あ、腰が痛いんですか。とりあえず画像でも」的な臨床は続いているし、患者側も「腰に何か起こったため腰が痛いんだ」と思い悩み、そういった検査を希望されるケースが多いのだと思う。
しかし・・・
この新しいガイドラインは2月1日発行の『Annals of Internal Medicine』に掲載された(らしい)。
「腰痛によって患者が病院に訪れることはもっともありふれたことであり、多くの腰痛患者はルーチンとしての腰部画像検査を受けることとなる。しかし、そういった検査は患者の役に立たないどころか、害を与えるおそれもある。」(Amir Qaseem)。
「とりあえず撮ってみる」どころか、害になることが在るというので注意が必要だ。
腰部の画像検査を受ける場合は、そういった害を超えた利益がなければならない。
X線(レントゲン)撮影やCTだって、性器の付近に放射線を浴びせるわけだから、注意が必要ということになる。
新しいガイドラインは、これまでのSR(システマティックレビュー)やmeta-analysis(メタアナリシス)といった質の高いとされる発表に基づきACP(アメリカ内科医学会)とAmecican Pain Societyにより作成された。
多くの勘案の結果、やはり『腰痛に対してルーチンとして行うX線(レントゲン)撮影、CT、MRIといった画像検査は、患者の健康状態を改善させない。それどころか、害になることもある。』ということになたのであろう。
もちろん、画像検査を必要とする状態もあるが、それらはあくまでも強調されるべき症状や状態である患者に対してであって、『腰部痛に対するルーチンとしての画像検査』似ついては大きな疑問符がついた・・・というより、『しない方が良い』とはっきりと宣言された形になる。
臨床としては、こういった情報を基に、それぞれの患者さんにどうするかを検討し、患者さんとともに話を進めていべきだと思う。
今回のガイドラインは、どのようにそういった臨床をすすめたら良いかという提案として、患者教育に使える”ガイドラインによる話題づくり”を推奨しているようだ。
オンラインやプリントを使用することによって、時間の少ないface to faceでの教育を補足することが可能となるとのこと。
・・・
本邦では、患者教育も必要だけれども、むしろ、腰痛の臨床に携わる人間への情報提供や教育も必要となると思う。
そもそも、EBMやガイドラインに対する誤解もあると思う。
どんなに情報が更新されようとも、頑にいつまでたっても、「腰部損傷モデル」でしか腰痛を語れない人もいる(というか多い)だろう。
医療従事者に対する『Talking Points』も考え、普及させなければならないのだろう。
参考
■medscape:ACP Issues Guidelines for Diagnostic Imaging for Low Back Pain
■ACP:Diagnostic Imaging for Low Back Pain: Advice for High-Value Health Care From the American College of Physicians

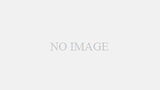
コメント